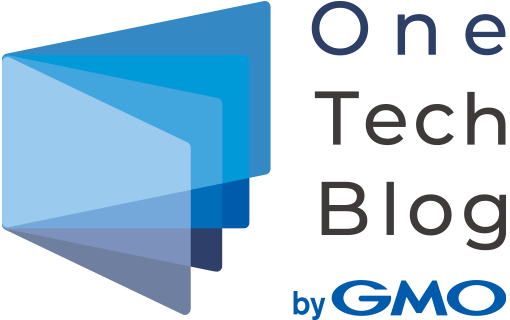こんにちは。CTO室長の浅野(@masakz5)です。
前回の記事ではC2PAの基本的な考え方と仕様について解説しました。その後もAIの進化は留まるところを知らず、誰もが本物と見分けがつかない画像や動画を、驚くほど低コストで生成できる時代になっています。このような状況だからこそ、コンテンツの「来歴(Provenance)」を証明するC2PAの重要性は、ますます高まっていると言えるでしょう。
こうした背景の中、C2PAは2025年6月2日、コンテンツの信頼性を技術仕様の段階から実際の運用・統治(ガバナンス)へと引き上げるための「C2PA適合性プログラム(C2PA Conformance Program)」を発表しました。
このプログラムは、C2PAの技術(コンテンツクレデンシャル)を用いてコンテンツを生成するソフトウェアやハードウェア(以下、ジェネレーター製品)が、C2PAの基準に沿って安全かつ信頼できる方法で来歴を記録しているかを、C2PA自身が保証する仕組みです。
この記事では、この新しいプログラムの5つの鍵と、それに伴う「信頼のリスト」の重要な移行計画について、わかりやすく解説します。
適合性プログラムとは?信頼への「お墨付き」
C2PA適合性プログラムは、デジタルコンテンツを生成するツールに対し、「あなたの製品はC2PAのルールとセキュリティ基準を遵守しています」という公式な「お墨付き」を与える、公平で透明性の高いプロセスです。
このプログラムの対象は、主に以下の3者です。
- コンテンツ生成製品 (Generator Product: GP):コンテンツの来歴を記録するカメラや編集ソフトなど。
- 検証製品 (Validator Product):記録された来歴データ(マニフェスト)を検証するツール。
- 認証局 (Certification Authority: CA):デジタル署名のための電子証明書を発行する機関。
適合性プログラムについてはC2PAのGoverning Authorityが統括し、ここから委任される形でC2PA技術作業部会(Technical Working Group)の適合性タスクフォース(Conformance Task Force)がAdministering Authorityとして運営を担当します。このプログラムに適合したと認められた製品は、後ほど説明する適合製品リスト (Conforming Product List: CPL)に掲載されることになります。
信頼を支える5つの新しい仕組み
適合性プログラムの発表により、コンテンツの信頼モデルをより厳格かつ公的に運用するための、5つの主要な要素が導入・明確化されました。
1. C2PA証明書ポリシー (C2PA Certificate Policy: CP) の公開
デジタルコンテンツの来歴データ(クレーム)の信頼性は、それが誰によって署名されたかにかかっています。これを証明するのが、署名に紐づく電子証明書です。
このC2PA証明書ポリシー(CP)は、証明書を発行する認証局(CA)が遵守すべき詳細なルールブックです。CPは、CAが申請者(ジェネレーター製品を実装する企業など。「サブスクライバー」と呼ばれます)に対して、C2PAクレーム署名用の証明書を発行するための手順を定めています。
このポリシーに従って運営されるCAだけが、後述するC2PAトラストリストへの登録を申請できるため、まさに信頼の根幹(ルート)を成すものと言えます。
2. C2PAジェネレーター製品セキュリティ要件 (GP-SR) の公開
コンテンツの来歴を記録するソフトウェアやハードウェアが、悪意のある第三者に乗っ取られ、来歴そのものを簡単に改ざんできてしまっては、信頼性は大きく損なわれます。そこで登場するのが、ジェネレーター製品セキュリティ要件 (GP-SR) です。
これは、コンテンツ生成製品(GP)がクリアすべき具体的なセキュリティ基準を定めた文書です。この要件には、GPにおける評価対象(Target of Evaluation: TOE)が、想定される脅威から保護されていることを証明するためのセキュリティ目標(Security Objectives: O)と具体的な要件(Requirements: R)が含まれています。
GP-SRを満たすことで、その製品が生み出したコンテンツの来歴データが、セキュリティ的に安全な環境で記録されたことが保証されるのです。
3. C2PAトラストリスト (TL) と TSAトラストリスト (TSA TL) の公開
C2PAのエコシステムにおいて、検証者(コンテンツの信頼性を評価する人やシステム。「依拠当事者」とも呼ばれます)が「この署名は本物だ」と判断する根拠となるのが、これらのトラストリストです。
- C2PAトラストリスト (C2PA Trust List: TL):適合ジェネレーター製品に対して、C2PA証明書ポリシー(CP)に基づき証明書を発行する、信頼できるルート認証局(トラストアンカー)のリストです。検証者はこのリストを参照し、コンテンツの署名が信頼できる機関によって行われたかを確認します。
- C2PA TSAトラストリスト (C2PA TSA Trust List: TSA TL):コンテンツが「その日時に存在したこと」を証明する、信頼できるタイムスタンプ局(TSA)のリストです。これにより、コンテンツがいつ作成・編集されたかという時刻情報の信頼性も検証可能になります。
4. 適合製品リスト (Conforming Product List: CPL) の公開
CPLは、適合性プログラムの厳しい審査を通過し、C2PAの基準を満たしていると認められたジェネレーター製品および検証製品の公式な「合格者名簿」です。
このリストに掲載されたジェネレーター製品のインスタンスのみが、C2PAトラストリストに登録されたCAからクレーム署名証明書を取得する資格を得ます。CPLには、その製品が達成できる最高の保証レベル、すなわち「最大アシュアランスレベル(Max Assurance Level)」も記録されます。
製品に「重大な変更 (material change)」があった場合は、CPLの記録を修正、または新規で再申請する必要があります。
5. 保証レベル (Assurance Level: AL) の策定
デジタルコンテンツの来歴を検証する側にとって、その情報がどれだけ信頼できるかを示す尺度が「保証レベル(Assurance Level, AL)」です。このレベルが高いほど、「この来歴情報は、本当にその製品が意図した通りに動作して生成されたものだ」という信頼度が高まります。
ALは、C2PAクレーム署名証明書の拡張領域(c2pa-al)を通じて伝えられます。
- 最大アシュアランスレベル (Max Assurance Level): 製品が技術的に達成可能な最高の保証レベル。GP-SRに基づき評価されます。
- AL 1とAL 2: 現在の仕様では、主にレベル1とレベル2の2段階が運用されています。
特に「アシュアランスレベル2(AL 2)」の証明書を発行するためには、認証局(CA)は、ジェネレーター製品のインスタンスが、パッケージ名やハッシュ値、コード署名証明書といった「検証可能なハードウェアに裏付けられた証拠(アーティファクト)」を提示し、厳格な検証プロセスを通過したことを確認する必要があります。
これにより、例えば「この写真は、セキュリティが確保された特定のスマートフォンカメラのチップで撮影された」といった、非常に強固なセキュリティ環境下でコンテンツが生成されたことを証明できるようになります。
暫定トラストリストからの移行
前回の記事で、暫定的に運用されるトラストリスト(トラストアンカー)について触れました。適合性プログラムの開始に伴い、いままで利用されてきた暫定トラストリスト (Interim Trust List: ITL)から、正式なC2PAトラストリスト (TL) への移行が計画されています。
ITLの役割と移行の必要性
ITLはC2PAの初期採用を支える重要な役割を果たしてきましたが、公式のC2PA TLは、より強固なガバナンスとセキュリティを提供します。C2PAは、ITLを廃止することで、エコシステム全体を最新のC2PA 2.x仕様へ準拠させることを目指しています。
移行のタイムラインは以下の通りです。
| 期間 | 内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 2025年12月31日まで | ITLの運用を継続 | この期間中、ITLに基づく古い証明書も検証サイトでは「信頼できる」と表示されますが、古い信頼モデルに基づいている旨の免責事項が併記されます。 |
| 2026年1月1日 | ITLを凍結 | 新しい証明書の追加や更新が停止されます。既存のITL証明書はレガシーサポートのために有効ですが、順次有効期限を迎え、最終的には署名に使用できなくなります。ただし、有効期間中に署名されたコンテンツは、古い信頼モデルにおいては常に有効と見なされます。 |
製品開発者やコンテンツを扱う実装者は、検証サイトと同様に、ITLベースの証明書(主にC2PA 1.4準拠)と、新しい適合プログラムに基づく公式TLの証明書を区別して扱うことが推奨されます。
まとめと今後の展望
C2PA適合性プログラムは、セキュリティに関して非常に緻密に設計されていることがわかります。
その一方で、特にAL2への対応は、デバイスメーカーやサービスプロバイダーにとって大きな開発負荷やコスト増につながる可能性があります。現時点では、AL1と比較した場合のAL2の明確なメリットがユーザーや開発者に示されていないため、積極的に対応する動機付けが生まれにくいかもしれません。
将来的に保証レベルごとに推奨されるユースケースが明確化されれば、この課題も解消されていくでしょう。
いずれにせよ、このプログラムの発表は、C2PAが技術標準の試験期間を終え、いよいよ実用段階へと移行したことを意味します。フェイク画像・動画対策の切り札としてC2PAへの期待は非常に高まっています。今後、実装が加速度的に進んでいくことを期待するとともに、GlobalSignとしてもその一翼を積極的に担っていきたいと考えています。